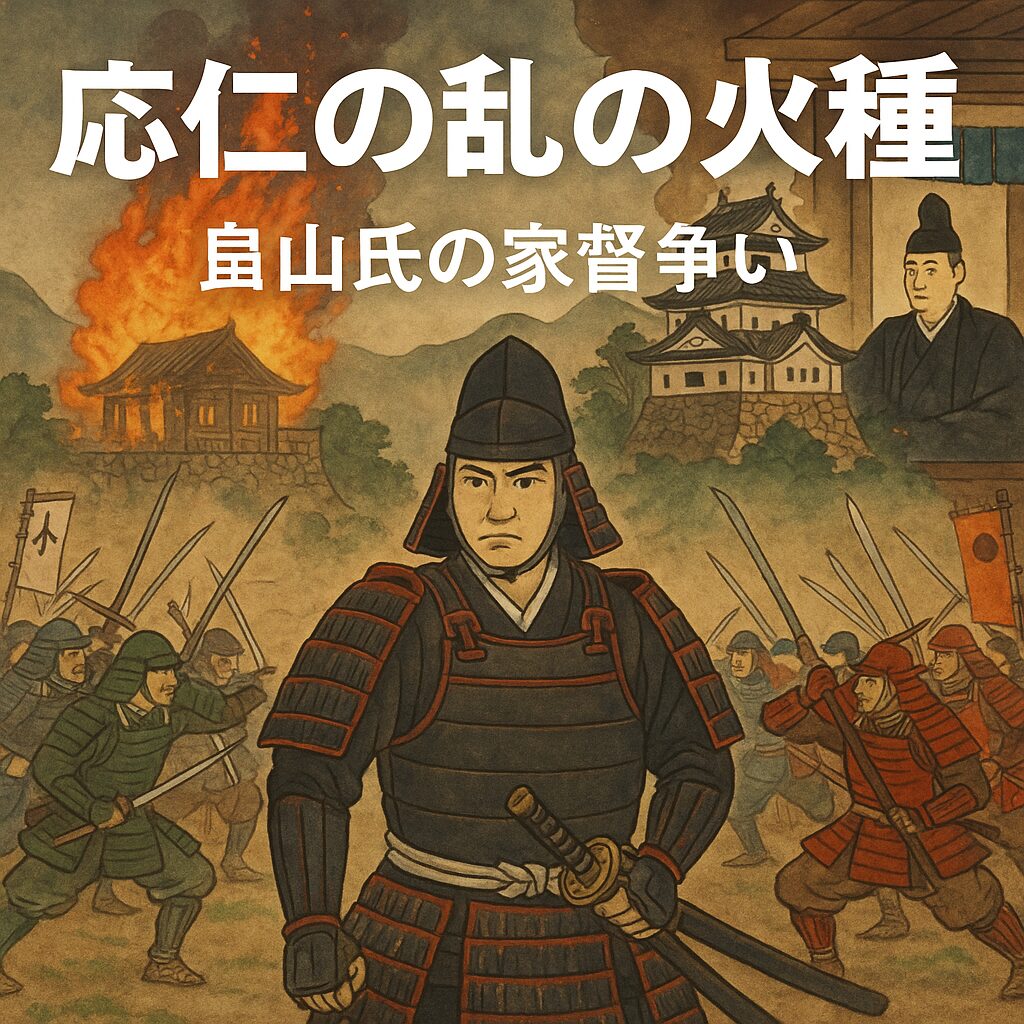戦国大名の誕生とは?下剋上の裏にある複雑な地域権力の変化

「下剋上」や「戦国大名の群雄割拠」と聞くと、武力で天下を狙う勇ましい武士たちの姿を思い浮かべるかもしれません。
しかし、実際の歴史はもっと奥深く、地域ごとに異なる複雑な権力構造の変化が背景にありました。
近年の研究では、「戦国大名」や「守護」という言葉の意味や役割の移り変わりが重要なテーマとして議論されています。
この記事では、そうした学術的な視点をわかりやすく解説していきます。
「戦国大名」とは何か?本当に“新しい”存在だったのか
戦国大名って、いったい何が新しかったの?
「戦国大名は力で土地を奪った武士」というイメージが定着していますが、実は歴史研究ではもう少し違った見方もされているんです。ここではまず、戦国大名という言葉の基本的な意味と、その誕生の背景を見てみましょう。
まず、長らく主流とされてきたのが、「戦国大名は、応仁の乱をきっかけに登場した新しい権力だった」という考え方です。
高校の教科書などでも、「応仁の乱で室町幕府の力が弱まり、各地に戦国大名が台頭した」と説明されることが多くあります。
この考え方では、「戦国大名」は、室町時代の守護とはまったく異なる、独立した強力な支配者と見なされています。歴史学者の長谷川博史氏などは、こうした支配者を「戦国期大名権力」と呼び、大きな地域を治めた勢力として強調しています。
守護の延長にある戦国大名という見方:「戦国期守護論」
戦国大名は、本当に“新しい”権力者だったのか?
近年の研究では、「戦国大名の多くは、室町時代の守護の延長線にある」という見方もあります。つまり、突然現れたのではなく、守護という伝統的な仕組みを引き継いでいたのかもしれないのです。
一方で、「いや、戦国大名は室町時代から続く守護の延長線上にある」とする見方もあります。これは「戦国期守護論」と呼ばれています。
この考え方では、戦国時代に現れた多くの大名たちが、実は室町時代から続く守護家の子孫や分家であり、その伝統や地位を活かして地域の支配を固めたとされます。
たとえば、歴史学者の今岡典和氏は、戦国時代の権力を理解するには、守護職や守護権の役割をきちんと見直すことが必要だと主張しています。彼によれば、室町時代と戦国時代のつながりを無視してしまうと、歴史の本質を見失うというのです。
守護と戦国大名の違いは?「下剋上」だけでは語れない実態
戦国大名と守護のちがいって何?
下剋上で力をつけた者たちが戦国大名になった…と思われがちですが、実は多くの大名が守護家の一族だったケースが目立ちます。その違いや背景を整理してみましょう。
「戦国大名」か「守護」か、という議論に終始するのではなく、「それぞれの言葉が、どんな歴史の問題に対して有効なのか」を考えるべきだという声もあります。
たとえば、守護が自分の本拠地(本国)にいた場合、支配は比較的安定していました(例:越後の上杉氏、駿河の今川氏など)。しかし、守護が自分の拠点ではない土地(非本国)を支配しようとした場合、現地の有力者が力をつけて独立してしまうことが多かったのです。
また、応仁の乱によって「守護が京都に滞在する制度(在京制)」が崩れ、各地の守護は地元に戻り、そこに自前の支配体制を築いていきました。
こうした中で「下剋上」が頻発したと言われますが、実際には「完全な下剋上」はそれほど多くなかったとも言われています。家督を継ぐのはあくまで守護家の一族や養子であり、「守護家」という存在自体はしぶとく生き残っていたのです。
実力だけでは不十分?戦国大名の正統性と幕府の認定

力だけじゃ大名にはなれなかった!?
どんなに実力で土地を治めても、幕府から「正当な支配者」として認められなければ、戦国大名とは言えません。朝倉氏の事例をもとに、その仕組みを詳しく見ていきます。
たとえば、越前(現在の福井県)を治めた朝倉孝景は、応仁の乱で東軍についたことで、将軍・足利義政から「守護代」として越前を任されます。さらに孫の代になると、「越前の支配権は誰のものか?」という問題で、幕府を巻き込んだ争い(長享・延徳の相論)も起きました。
結果的に朝倉氏は、幕府の「御供衆」や「御相伴衆」として認められ、守護家としての家格を手に入れます。つまり、朝倉氏が越前の支配者になれたのは、力だけでなく幕府からの“お墨付き”があったからなのです。

御供衆(おともしゅう)
主君(将軍・大名)が外出や参詣、また戦などで出かける際、常に供をして警護や雑務をつとめる武士の集団です。
御相伴衆(ごしょうばんしゅう)
主君の食事や儀式・宴席などに同席することを許された家臣階級の一つです。
守護職よりも「家格」が支配の正当性を支えていた
戦国時代、力を持っていたのは「家」だった?
守護という役職よりも、「守護家」としての“家格”が支配の正当性を支えました。こうした家格重視の構造は、実は多くの大名に共通していたのです。
戦国時代になると、守護職そのものよりも、「守護家という“家格”」が重視されるようになりました。
たとえば、出雲の尼子氏も、守護職に正式に就く前から、すでに「守護家」として地域支配を担っていたことが分かっています。

このように、戦国時代の地域権力は「家の力」で支えられた部分が多く、守護の伝統や幕府との関係が、見た目以上に深く関わっていたのです。
まとめ:戦国時代は、守護の延長線上にあった
戦国時代は「断絶」ではなく「連続」だった
下剋上や戦国大名の登場といったドラマチックな変化の裏には、室町時代から続く家格や幕府との関係といった、意外に保守的な要素が根強く残っていました。
今回ご紹介したように、戦国時代の地域支配を「下剋上」や「戦国大名の新登場」だけで語るのは早計です。
多くの戦国大名は、室町時代から続く守護家やその家格、そして幕府との関係性をうまく活かして、支配を正当化していました。力だけで成り上がることは難しく、あくまで「家」や「幕府とのつながり」が重要だったのです。
これらの視点を持つことで、戦国時代のイメージはより立体的で現実に近づいていきます。もしあなたが日本の歴史をより深く知りたいなら、「誰が力を持っていたか」だけでなく、「なぜその力が正当とされたのか」も考えてみると、見える景色が変わってくるかもしれません。