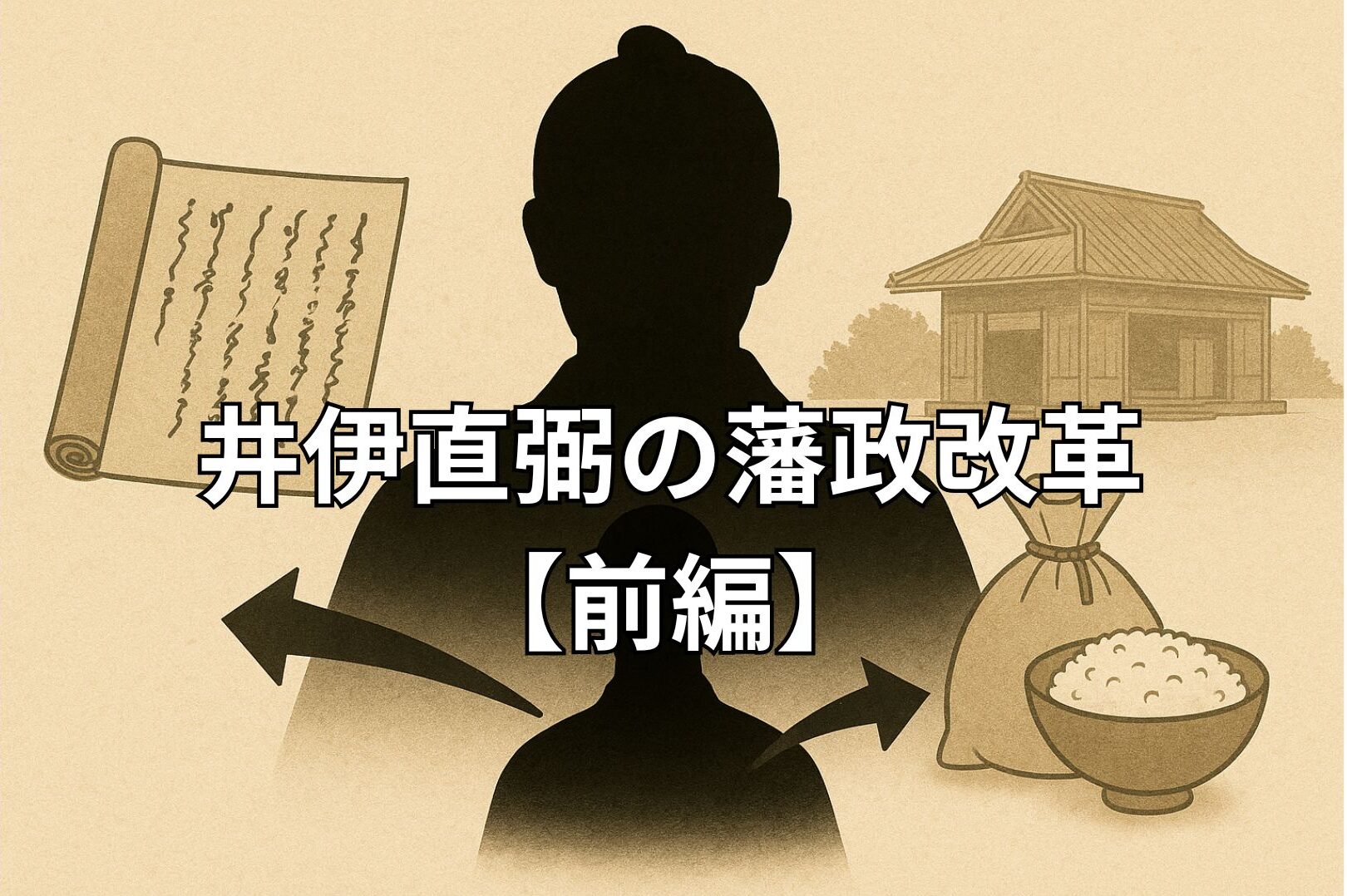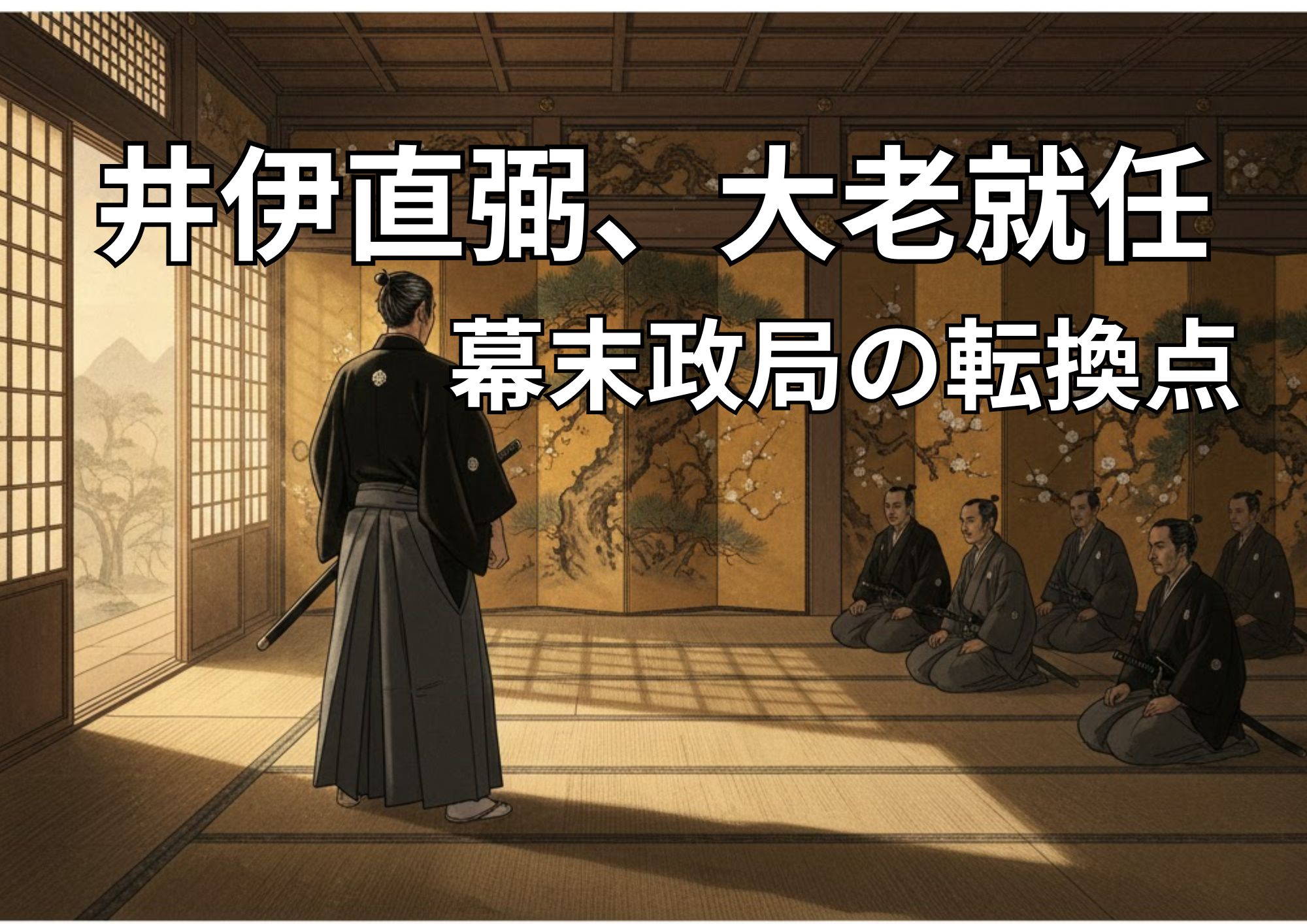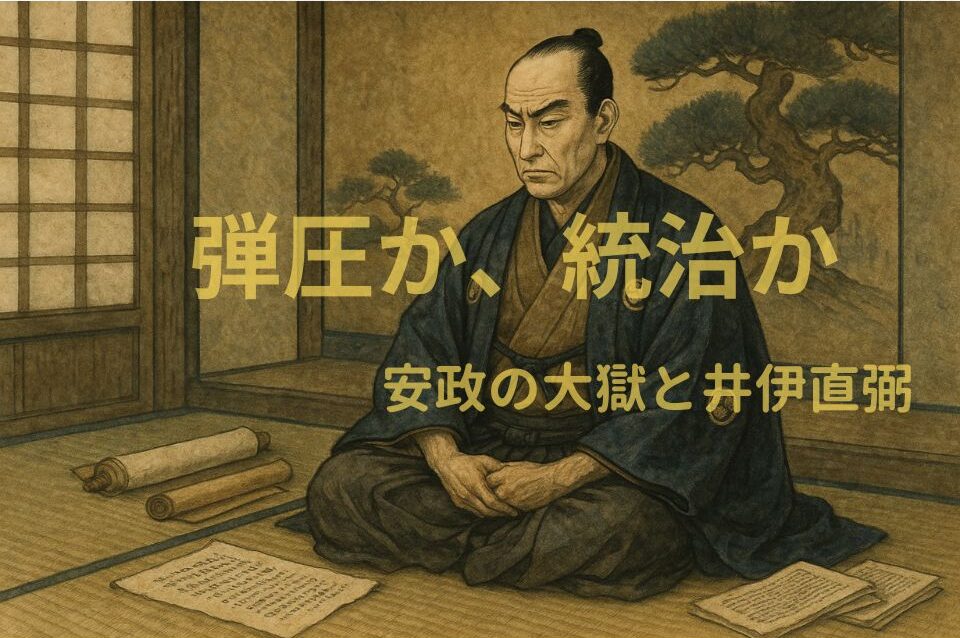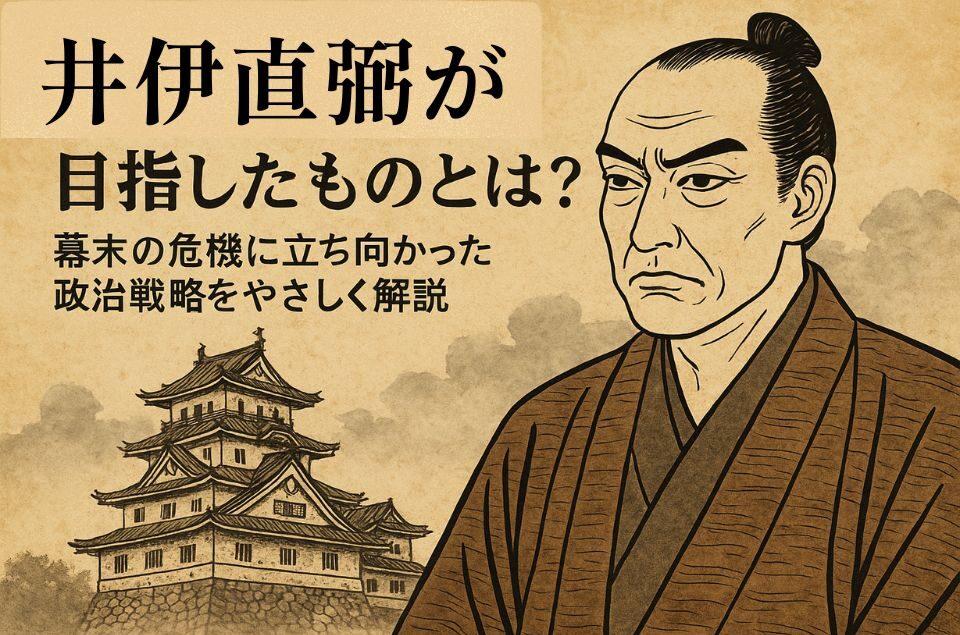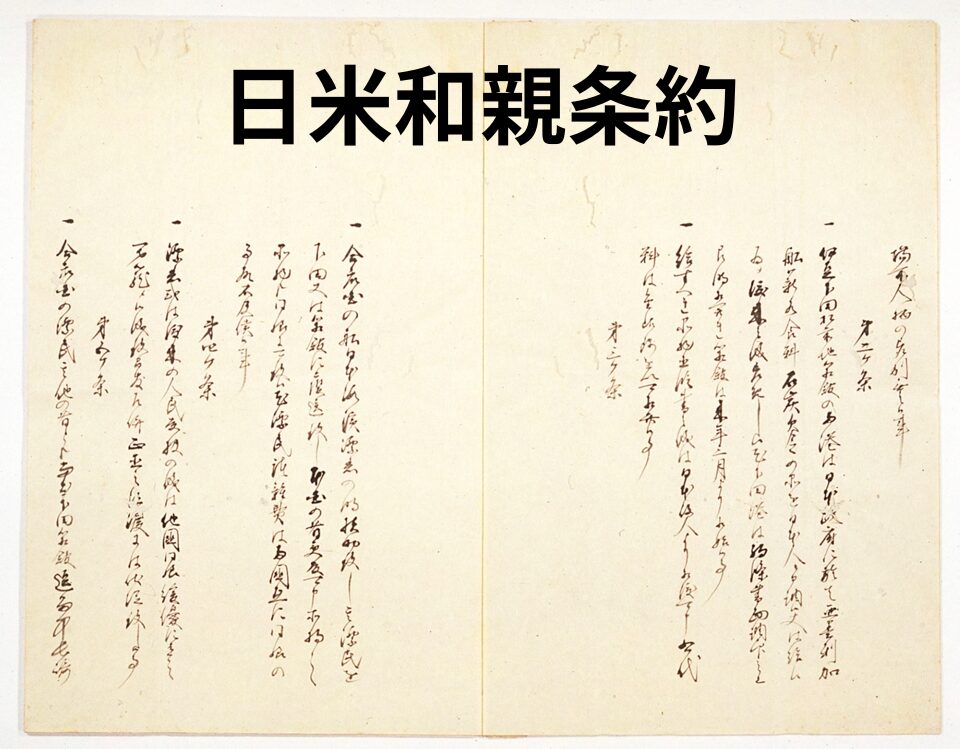👑 明治天皇、彦根へ──行幸が救った城

🏯「廃城令」の波の中で
明治6年(1873年)、新政府は**太政官布告により「廃城令」**を出しました。
これは「全国の不要な城郭を取り壊すように」という指示で、封建制の名残を一掃し、近代国家への道を進む上での大きな政策転換でした。
この令によって、約170城以上が破却・解体され、天守や櫓が姿を消していきました。
彦根城も例外ではなく、一時は取り壊しの対象となっていたのです。
👑 明治天皇の行幸──城を守った“巡幸の奇跡”

明治11年(1878年)、明治天皇は**北陸・東海地方の巡幸(行幸)**に出られました。
この巡幸は、新政府の権威を地方に示し、民心を掌握するという政治的な意味を持っていました。
その行幸ルートに彦根も含まれており、天皇を迎えるにあたって「城が必要」と判断されたのです。
こうして、取り壊し寸前だった彦根城は一時保存されることとなりました。
🌸 なぜ「城」が必要だったのか?
当時、天皇の行幸先では「宿泊施設や拝謁の場として、格式ある建造物」が求められていました。
彦根城の天守や御殿はその条件に適しており、“実用的な理由”で残されたのです。
そしてもう一つ──
彦根藩主だった井伊家の功績と格式が、明治政府の中でも重んじられていたという背景もあります。
旧譜代大名としての信頼と実績は、新時代の政治においてもなお影響力を持っていたのです。
🧑🤝🧑 地元と旧藩士たちの“誇り”
.png)
さらに、彦根城が残った裏には、旧彦根藩士や地元有力者たちの熱意がありました。
- 「井伊家の誇りとして、城を守りたい」
- 「歴史ある彦根の象徴を未来に残したい」
そんな思いが実際の運動として現れ、資金面の支援や保存のための働きかけが行われました。
結果として、明治政府も「彦根城は保存の価値がある」と判断するに至ったのです。
🏆 明治から昭和へ──文化財としての再評価
明治時代後期から、全国的に歴史的建築物への関心が高まり始めます。
彦根城も例外ではなく、昭和27年(1952年)には天守が「国宝」に指定。
以降、文化財としての価値が再評価され、保存活動も本格化しました。
今では、彦根城は江戸時代の姿を最も良く残す現存天守の一つとして、世界中から注目されています。

🔖 まとめ:「行幸」という名の“奇跡”
もしも明治天皇が彦根を訪れていなければ──
彦根城は、他の多くの城と同じように取り壊されていた可能性が高いのです。
しかし、
- 天皇の行幸という国家的イベント、
- 井伊家の歴史的評価、
- 地元の保存運動、
これらが重なり合い、彦根城は廃城の運命を免れました。
城を救ったのは、“歴史の偶然”ではなく、“誇りと継承”の力だった。
今も天守に立ち、琵琶湖を望むとき、そこには明治の空を翔けた一つの物語が息づいているのです。