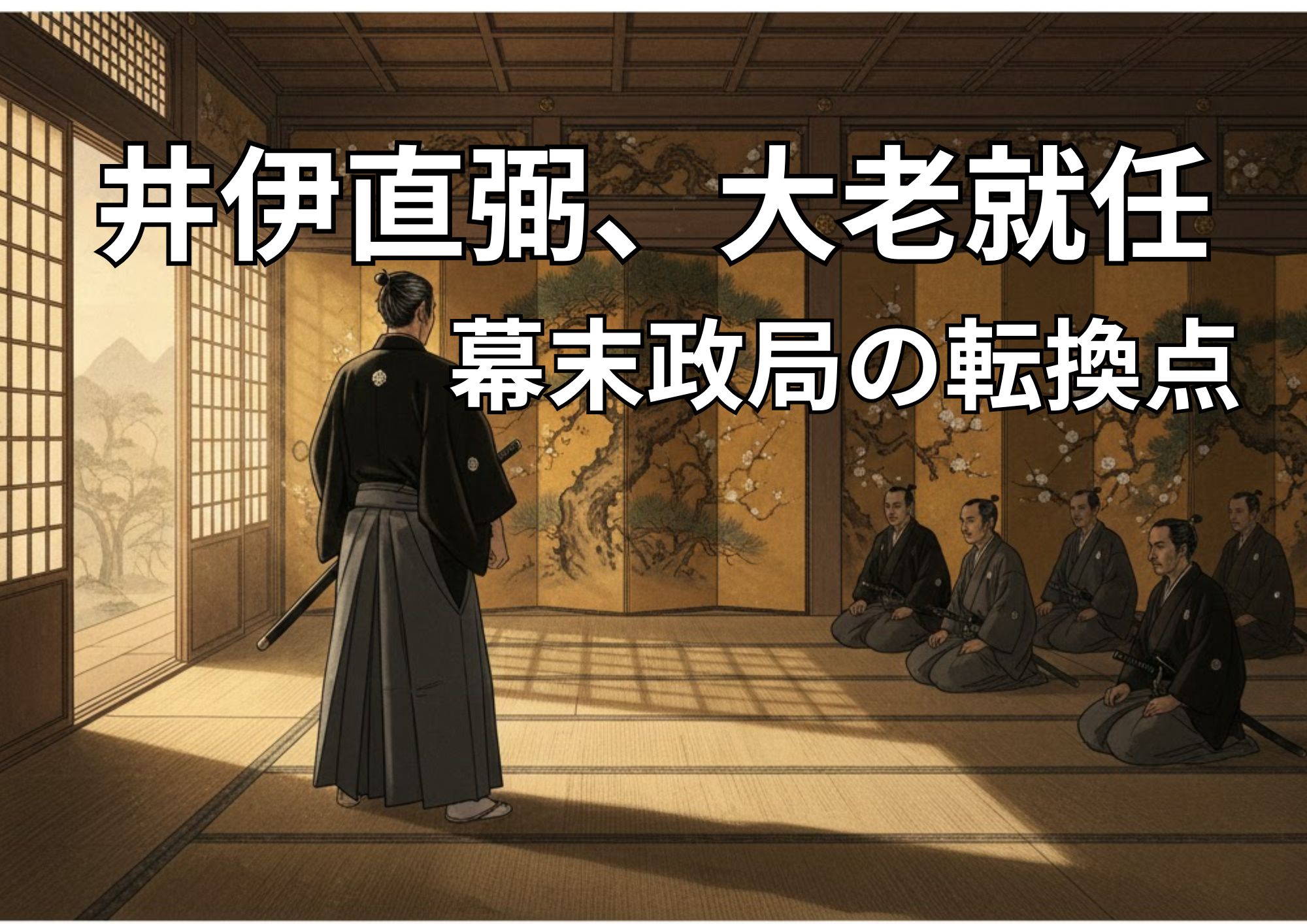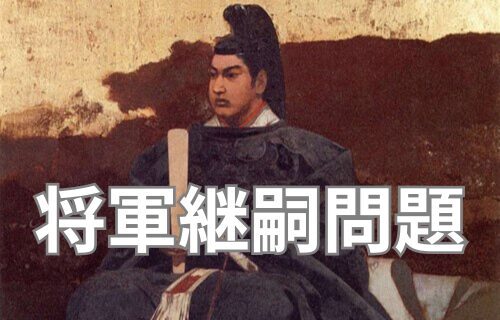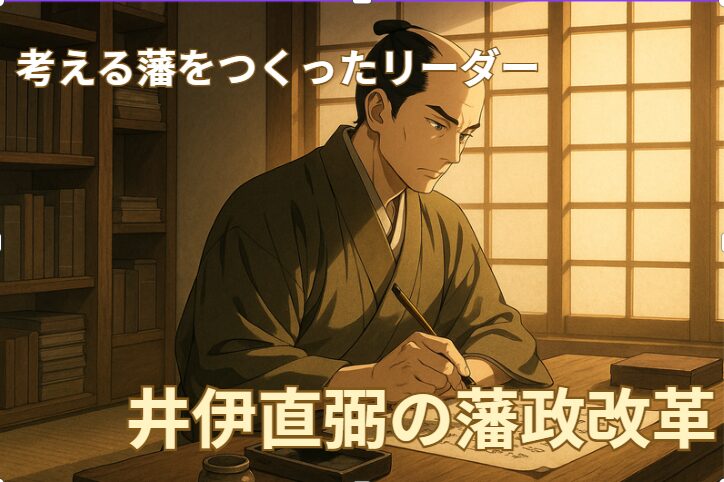タウンゼント・ハリス(1804–1878):アメリカ初代駐日総領事の生涯

🌱 幼少期とニューヨークでの活躍
生誕・出自
1804年10月3日(米英文献では10月4日)、ニューヨーク州ワシントン郡サンデイヒル(後のハドソン・フォールズ)に生まれる。家計は裕福ではなく、13歳で兄の陶磁器輸入業を手伝い、見習いとして働くことになった。
独学と教育への情熱
貧困家庭出身ながら独学で仏・伊・スペイン語を習得し、1846年から48年までニューヨーク市教育委員会の委員長を務める。1847年には市民のための「フリーアカデミー」(現・ニューヨーク市立大学シティ・カレッジ)を創設し、自ら語学の授業も担当した。
🌏 商人としての冒険と外交志向
貿易事業の試み
教育活動後は太平洋・インド・中国・シャム(タイ)などを商船で巡るが、経営は苦戦し、上海に滞在中にマシュー・ペリー提督の日本行に触発され、外交への道を志す。

最初の外交任務:シャム(タイ)との交渉
1855–56年にかけてシャムでロバーツ条約改訂に関与し、「ハリス条約(1856)」をまとめ、駐シャム米国領事としての信用を高めた。
🇯🇵 日本駐在と「ハリス条約(1858)」の締結
駐日総領事就任
1856年、フランクリン・ピアース大統領により初代駐日米国領事に任命され、1856年夏、下田に上陸した。しかし幕府は警戒感を示したが、やむを得ず玉泉寺を公使館として認めた。

孤軍奮闘と交渉の継続
1856年から約3年、公使館設置を巡る軋轢の中、交渉を粘り強く続け、ついに1858年に日米修好通商条約(ハリス条約)を締結した。これにより開国が進み、神奈川(横浜)・長崎・新潟・兵庫と国際的に開港され、貿易が開始されました。
ただし、不平等条約であり、明治政府がこれを解消するのは日露戦争勝利の後でした。
- 関税自主権がなかった👉 輸出入の税率は日本が自由に決められず、アメリカとの合意(貿易章程)で固定された。
- 領事裁判権(治外法権)をアメリカに認めた👉日本で罪を犯したアメリカ人を、日本の法律ではなくアメリカの法律・領事裁判で裁く。
- 外交関係の樹立👉日米両国に公使を日本に米国領事を置くことを認めた。
- 航行の支援・保護と日欧間でのトラブルを仲裁の義務👉アメリカ軍艦は日本船航海を支援・保護すること。日欧間でのトラブルをアメリカ大統領が仲裁する。
-e1747230874105.jpg)
🏮 日本での評価と帰国後
日本側の感謝
幕末の日本はハリスを「友人かつ恩人」と評し、その働きは今も評価されている 。

健康問題での帰国
交渉の途中で体調不良となるなど健康を害し、1861年に帰国する。以後はニューヨークで静養生活を送り、1878年2月25日に73歳で没する。
死後の称賛と記念
ハリスが眠るニューヨーク・ブルックリンのグリーンウッド墓地には、日本政府より供えられた石灯籠や桜の木など記念物が設置されている 。

🎭 文化的影響と伝説
芝居や映画での扱い
1895年に日英舞台化され、1919年には日本人脚本による劇、1958年にはジョン・ウェイン主演の映画『The Barbarian and the Geisha』(邦題「荒野の侍」)で描かれた。
「お吉」の伝説
ハリスと下田にいた女性「唐人お吉」については、さまざまな噂や伝説があるが、史実は曖昧であり、むしろ架空のストーリーに近いとされる。

✅ 総括
タウンゼント・ハリスは、教育者としての功績(貧困家庭にも高等教育を開放)と、外交官としての挑戦(孤独な交渉を経て日本の開国を促進)の両面で歴史に名を残した人物です。その胆力と交渉力は、幕末の日本で西洋に開かれた最初の扉をこじ開けました。また、多岐にわたる影響を後世に残しました。
📚 参考文献・出典
- Wikipedia(英語)
- Wikipedia(日語)
- Britannica(英語)
- 下田市ウェブサイト