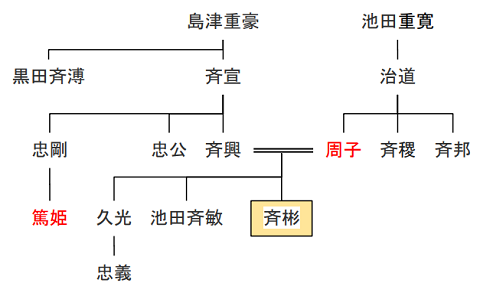【第4回】開国か攘夷か?井伊直弼が選んだ「現実の決断」──日米修好通商条約の真実
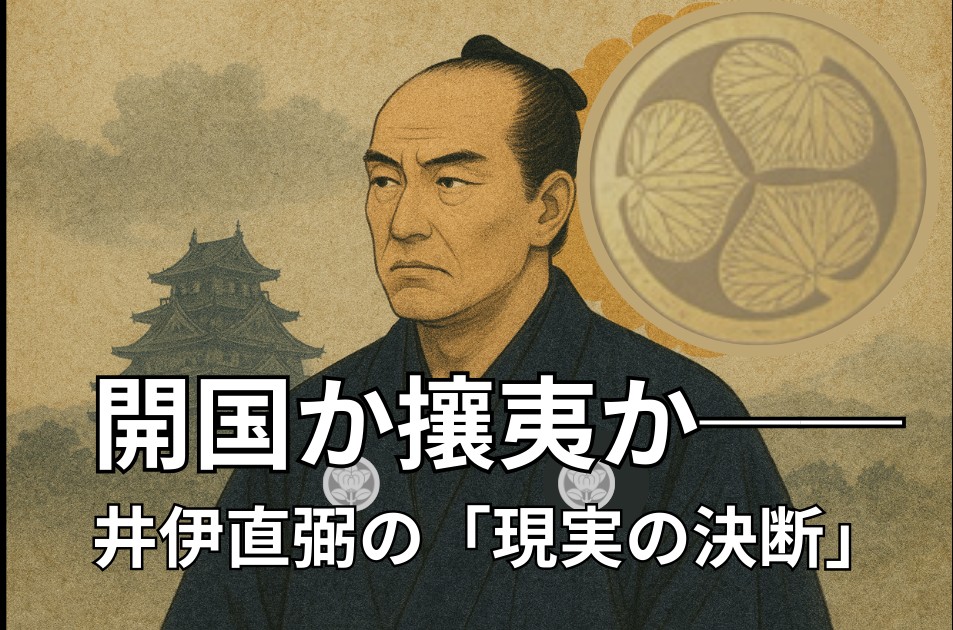
「国を誤るは小才子の所業なり」
幕末日本──
ペリーの黒船来航によって、日本は突如として「開国か、攘夷か」という国家の岐路に立たされました。
この危機のなかで、大老に就任した井伊直弼は、
「不完全でも条約を結び、戦争を避ける」
という、きわめて現実的な決断を下します。
本記事では、
✅ 日米修好通商条約はなぜ“勅許なし”で調印されたのか
✅ それは本当に「独断」だったのか
✅ 反対派はなぜそこまで激怒したのか
を、一次資料に基づいた視点で解説します。

🌊 黒船来航と迫る危機──アヘン戦争の衝撃

1853年(嘉永6年)、ペリー黒船が浦賀に来航したことで、日本社会は大きく揺さぶられました。
その背景には、清国がアヘン戦争でイギリスに惨敗したという国際情勢があります。
幕府もすでに
- 海防強化
- 様式砲術
- 軍制改革
など進めていましたが、 日本全体としては列強と戦える体制ではありませんでした。
この認識は、のちに井伊直弼が提出した
👉『別段存寄書』
にも明確に表れてます。
関連記事▼
井伊直弼はなぜ開国を選んだのか?ペリー来航と「別段存寄書」に見る戦略
📜 通商条約の批准──「朝廷の許しなくとも」

1858年(安政5年)、井伊直弼が大老に就任すると、通商条約問題は最終局面を迎えます。
ここで重要なのは、
✅ 条約は井伊直弼の「個人的独断」で締結されたわけではない
という点です。
実際には、
- 老中合議
- 将軍・徳川家定の裁可
- 幕府としての正式手続き
という 制度上の手続きを踏んだうえで調印されています。
ただし、唯一欠けていたのが勅許でした。
🚨 武力衝突の回避か、祖法の維持か──時間との戦い
ハリスは交渉の停滞に対し、

「交渉が進まなければ、軍事行動もやむを得ない」
という趣旨の強い圧力を示唆していました。
これは公式な宣戦通告ではありませんが、当時の国際情勢を踏まえれば、
という認識は、幕府首脳に共有されていたと見てよいでしょう。
井伊直弼はこの状況下で、
- 勅許を待ち続けて衝突の危険を高めるか
- 不完全でも条約を結び、戦争を回避するか
という、極めて苦しい二択を迫られていました。
そして彼は、尊王でありながら
「戦争回避」を最優先する道を選びます。
| 発生日 | 内容 | 原因 |
|---|---|---|
| 安政四年十月二十一日 | 将軍家定がハリスに謁見 | 通商条約交渉の正式開始 |
| 安政五年正月五日 | 条約調印を60日延長 | 勅許待ちのため |
| 安政五年三月十四日 | 孝明天皇の勅答→留保 | 先に諸大名の合意を取ること |
| 安政五年三月中旬 | 約3か月再延長(→6月末) | 天皇の拒否 |
| 安政五年四月二十三日 | 井伊直弼が大老就任 | 将軍の指名 |
| 安政五年六月十九日 | 条約調印 | 結果的に勅許なし |
▶関連記事
井伊直弼の政治力|条約調印と将軍継嗣を決断した「嵐の中の船長」
🧭 名君か独裁者か──“強引さ”の内実
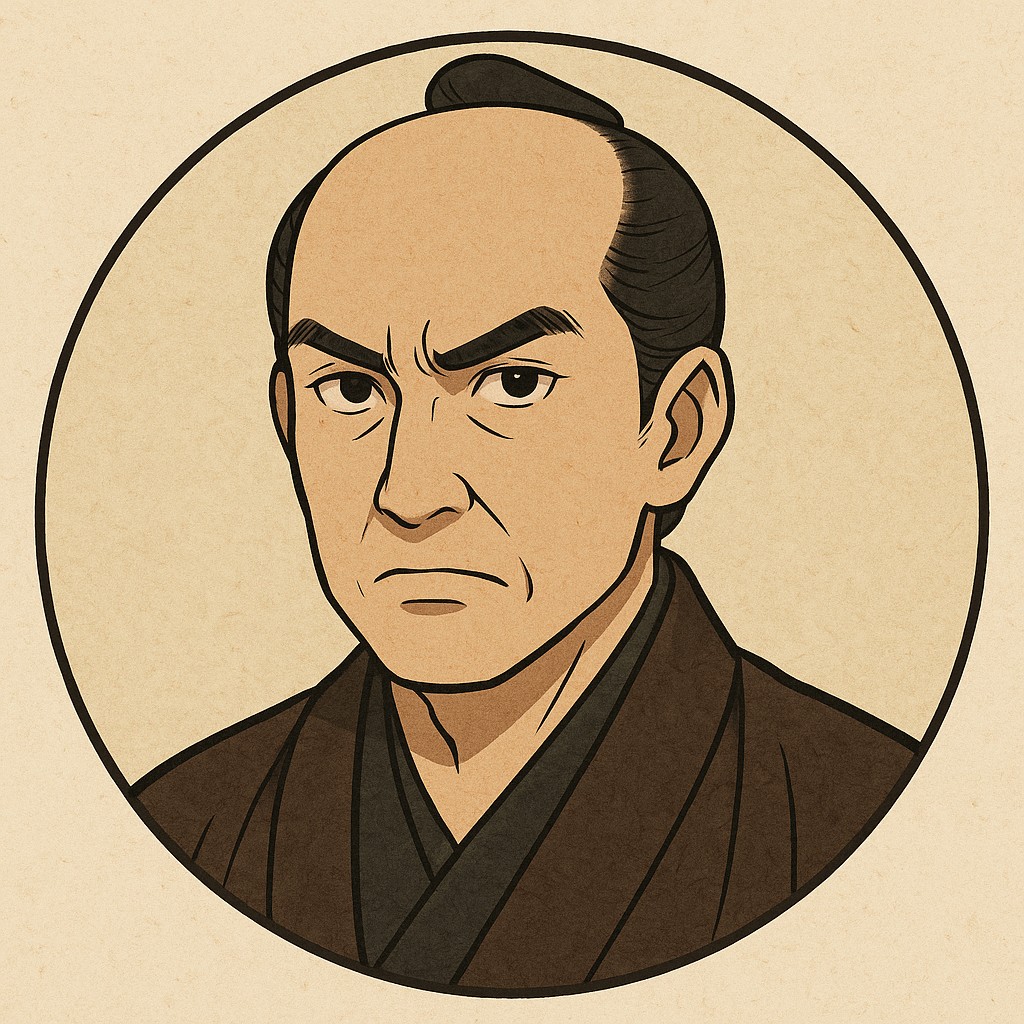
批判は甘んじて受け入れる
この決断により井伊直弼は
「強引な独裁者」
という評価を背負うことになります。

「公用方秘録」に彦根藩邸に戻ってから側近の宇津木景福とのやり取りが詳しく記されています。
しかし一時史料から確認できるのは、
彼の判断が、当時の軍事力・財政力・国際情勢を踏まえた極めて現実的な国家判断だったという事実です。
一方で、朝廷や尊王攘夷派から見れば、
- 攘夷こそが「祖法」
- 外国との条約は「国体破壊」
と映りました。
不思議なことに尊王攘夷派と言われている福井藩主・松平慶永(春嶽)は「昨夢紀事」の中で朝廷の政治的台頭を警戒してます。
ここに、
✅ 現実主義 vs 非現実主義
✅ 幕府外交 vs 朝廷倫理
という、決定的な価値観の断絶が生じていたのです。
この断絶こそが、やがて
- 安政の大獄
- 桜田門外の変
へと連なっていく、思想的起点でした。

▶こちらも読んでください。
井伊直弼と「彦根藩邸評議」──条約調印当日の意思決定と宇津木景福の進言
🧩 まとめ──時代を切り裂いた決断

安政5年(1858年)に締結された日米修好通商条約は、たしかに不平等条約でした。
しかし同時に、それは日本が
✅ 植民地化を免れ
✅ 主権国家として近代化する
ための**「時間を稼いだ条約」**でもありました。
井伊直弼は、
- 栄誉を得るためではなく
- 賞賛されるためでもなく
- ただ「戦争を避けるため」にすべての非難を引き受けた政治家でした。
関連記事:
【第3回】大老就任─非常時に登場した“臨時最高責任者”
【第5回】安政の大獄は「違法」だったのか?─幕末法制度と井伊直弼の政治判断
📘 史料出典についてのご注意
「国を誤るは小才子の所業なり」は井伊直弼の名言として知られていますが、一次史料には見えず、近代以降の伝承本にのみ確認される表現です。
学術的には出典未詳の言葉として扱われるため、引用にあたっては史料的な背景をご理解いただく必要があります。
本稿の内容は『幕末維新史料集』『井伊家史料』『続徳川実紀』『ハリス日本滞在記』などの一次史料・研究書をもとに構成しています。