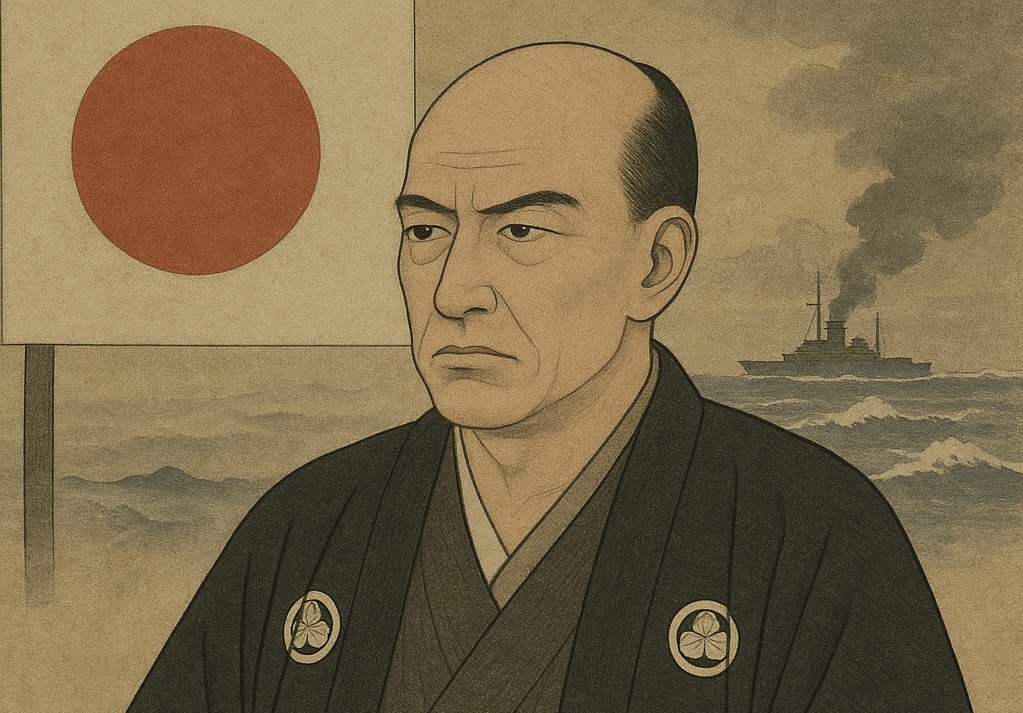【第1回】埋もれ木の少年──井伊直弼、その静かな出発点
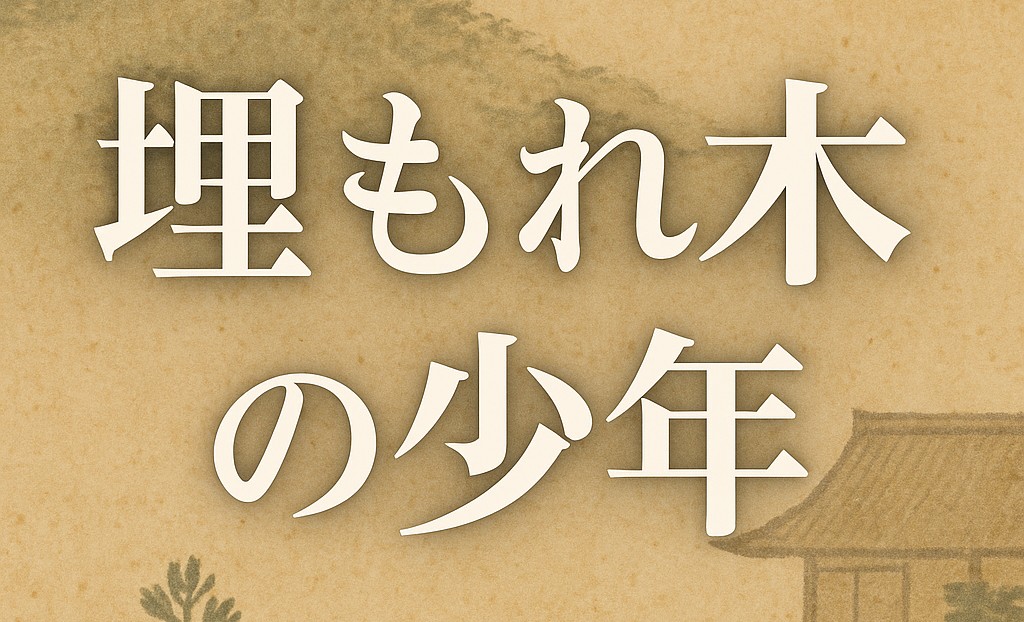
「世の中を よそに見つつも 埋もれ木の
埋もれておらぬ 心なりけり」
――井伊直弼
Contents
🔰 このシリーズでわかること
本シリーズ「埋もれ木の少年」では、幕末の風雲の時代に翻弄されながらも、自らの信念を貫いた一人の武士、井伊直弼の生涯を追っていきます。
第1回となる今回は、彼の「出発点」としての少年期、そして後の人格形成に大きく影響を与えた「埋木舎(うもれぎのや)」での暮らしに焦点を当てます。
🌸 井伊家の十四男として──世継ぎの望みなき少年
1815年(文化12年)、彦根藩主・井伊直中の十四男として生まれた直弼。幼少期から、彼には「家を継ぐ望み」はありませんでした。
それは、「家督を継ぐ者」ではなく「ただの家臣」として、藩政の外側で生きる人生を意味します。
彼に与えられたのは、藩邸の一隅にある小さな屋敷──後に「埋木舎」と呼ばれることになる場所でした。
🏡 埋木舎での暮らし──孤独ではなく、自省と鍛錬の場
「世の中を よそに見つつも――」
井伊直弼の和歌からは、孤独を嘆くどころか、「世間から離れた場所で、己を鍛える」という強い意志がうかがえます。
埋木舎では、茶道・禅・武道・和歌と、あらゆる分野において研鑽を重ねた直弼。
特に、彼が熱心に学んだ「石州流茶道」は、後の政治姿勢に通じる“静と動のバランス”を育んだとも言われています。

やがて、直弼に思いもよらぬ転機が訪れます。
藩主の兄たちが次々と亡くなり、家督継承者として白羽の矢が立ったのです。
藩政の表舞台に出ることとなった直弼は、少年時代に培った学びと精神力をもって、幕末日本の命運を握る「大老」へと登りつめていくのです。
🔗 次回予告:「藩政改革と名君の素顔」
次回は、藩主となった井伊直弼が、いかにして彦根藩を建て直したのか──その「名君」としての一面をお届けします。
埋もれ木は、どのようにして芽を出したのか。ぜひ、次回もご期待ください!
🔖 補足:直弼と彦根の絆
井伊直弼の人生は、常に彦根という地と深く結びついていました。
明治の世になっても、彼の面影は「埋木舎」や「彦根城」に残り続け、今も多くの人々に語り継がれています。
🔗 関連記事:
👉 明治天皇、彦根へ──行幸が救った城
💡 ブログ運営者より
このブログでは、井伊直弼を「赤鬼」としてではなく、一人の“志を持った人物”として再発見していきます。
ぜひ他の記事もご覧ください!